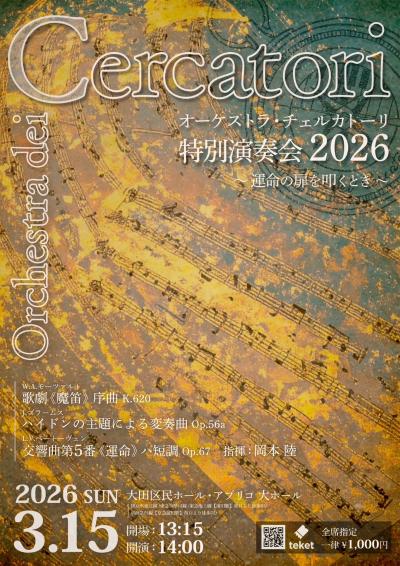作曲家検索
作曲家一覧
471-480件 / 1157件中
エイノユハニ・ラウタヴァーラ
1928年10月9日 - 2016年7月27日
フィンランド

エイノユハニ・ラウタヴァーラ(Einojuhani Rautavaara 1928年10月9日 - 2016年7月27日)は、フィンランドの現代音楽の作曲家。同国における同世代の作曲家のなかでは代表的存在である。ヘルシンキに生まれる。1948年から1952年まで、ヘルシンキのシベリウス・アカデミーにてアーッレ・メリカントに師事。後に、シベリウスの勧めでニューヨークのジュリアード音楽院に移る。ジュリアード音楽院では、ヴィンセント・パーシケッティに師事するほか、タングルウッド音楽センターにてセッションズとコープランドのレッスンも受けている。
高嶋圭子
日本

高嶋 圭子(たかしま けいこ)は、日本の作曲家、編曲家。ハラヤミュージックエンタープライズ所属。東京藝術大学音楽学部作曲科卒業。世界的に有名なパリ・トロンボーン四重奏団に献呈作品を提供している。1996年のひろしま国体では開会式、閉会式のファンファーレを作曲。
ハインツ・ホリガー
1939年5月21日
スイス

スイス・ランゲンタール出身。ベルン音楽院とバーゼル音楽院で音楽教育を受ける。ヴェレシュ・シャーンドルと、ピエール・ブーレーズに作曲を師事。オーボエはスイスでエミール・カッサノウ、パリ音楽院でピエール・ピエルロ、ピアノをイヴォンヌ・ルフェビュールに師事。 オーボエ奏者としての卓越した演奏・楽曲解釈とともに、作曲家としても著名であり、また指揮者としても活動しており、ポーランドなど東欧の現代作曲家の作品などを積極的に紹介してきた。教育者としては、1966年からドイツのフライブルク音楽大学で教鞭を執っていた。
マックス・スタイナー
1888年5月10日 - 1971年12月28日
オーストリア

マックス・スタイナー(Max Steiner、1888年5月10日 - 1971年12月28日)は、オーストリア生まれのアメリカ合衆国の映画音楽作曲家。本名はマクシミーリアン・ラウル・ヴァルター・シュタイナー(Maximilian Raoul Walter Steiner)。
ハンス・ジマー
1957年9月12日
ドイツ

ハンス・ジマー(Hans Florian Zimmer、ハンス・フロリアン・ツィマー、1957年9月12日 - )は、ドイツ出身の作曲家。 これまでに計12回のアカデミー賞ノミネート(内受賞2回)、計15回のゴールデングローブ賞ノミネート(内受賞3回)、計4回のグラミー賞受賞など、数多くの受賞経験を有する最も著名な映画音楽作曲家の一人である。
ジャン・バティスト・アーバン
1825年2月28日 - 1889年4月9日
フランス

ジョゼフ・ジャン=バティスト・ロラン・アルバン(Joseph Jean-Baptiste Laurent Arban, 1825年2月28日 - 1889年4月9日, 英語読みのアーバンで知られる)は、フランスのコルネット奏者、指揮者、教育者。ピストン式コルネットの最初の巨匠である。ヴァイオリンの名手パガニーニに影響を受けてコルネットの技巧的な奏法を開拓し、コルネットが真のソロ楽器たりうることを証明した。
Ayase
1994年4月4日
日本

Ayase(あやせ、1994年〈平成6年〉4月4日 - )は、日本の男性ミュージシャン ボーカロイド・プロデューサー、音楽ユニット・YOASOBIのコンポーザー。2018年12月よりボーカロイド楽曲の投稿を開始した。また、ダンスボーカルグループ・原因は自分にある。やYouTuber3人によるボーカルユニット・TTJなど他アーティストへの楽曲提供も行っている。
後藤洋
日本

後藤 洋(ごとう よう、1958年 - )は、日本の作曲家、編曲家、音楽評論家。主として吹奏楽の分野で活動している。 2001年以来アメリカに本拠を置き、吹奏楽と音楽教育の分野を中心に作曲・編曲家、音楽評論家、研究家として活躍。吹奏楽の分野では、今日国際的に評価を得ている日本人作曲家のひとりであり、その作品はアメリカとヨーロッパ諸国で注目を集めている。海外で出版される吹奏楽作品の紹介、また音楽教育としての吹奏楽の研究においても、日本における第一人者。
PRおすすめのコンサート

第22回みなとみらいアイメイトチャリティーコンサート

石田泰尚(ヴァイオリン)と上原彩子(ピアノ)によるチャリティーコンサート