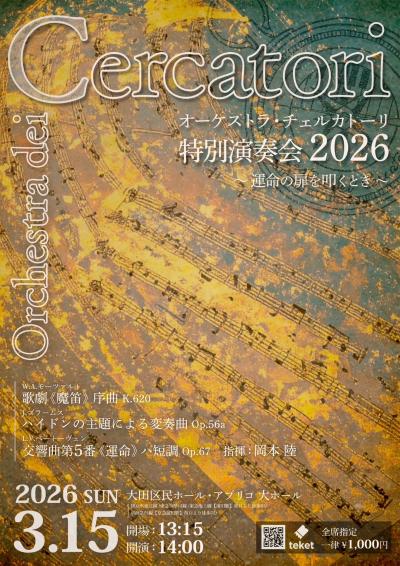作曲家検索
作曲家一覧
501-510件 / 1157件中
吉俣良
1959年9月6日
日本

吉俣 良(よしまた りょう、1959年9月6日 - )は、日本の作曲家・編曲家・音楽プロデューサー。鹿児島県鹿児島市甲突町出身。横浜市立大学商学部卒業。血液型はO型。「Ryo」名義で作曲・編曲を行う事がある。
アルフレッド・デザンクロ
1912年2月7日 - 1971年3月3日
フランス

アルフレッド・デザンクロ(Alfred Desenclos, 1912年2月7日 - 1971年3月3日)は、フランスの作曲家。パ=ド=カレー県のポルテル(fr:Le Portel)に生まれる。1929年にルーベ音楽院に入学後、1932年にパリ音楽院へ進学する。アンリ・ビュッセルらに師事して作曲を学ぶ。1942年にローマ賞大賞を受賞。1943年から1950年までルーベ音楽院院長を務めたが、作曲に専念するため辞職。1956年に《交響曲》によりパリ市音楽大賞(Grand prix musical de la ville de Paris)を受賞。1967年にパリ音楽院の和声科教授に就任した。1971年パリにて逝去。
ヨハン・スヴェンセン
1840年9月30日 - 1911年6月14日
ノルウェー

ノルウェーの作曲家、指揮者、ヴァイオリニスト。スウェーデン統治下ノルウェーのクリスチャニア(現オスロ)に生まれ、生涯のほとんどをデンマークのコペンハーゲンに過ごし、70歳で同地にて他界した。 親友にしてより高名な作曲家のグリーグとは対照的に、スヴェンセンは響きの美しさというよりは、管弦楽法の技巧によって名を揚げた。グリーグがたいてい小編成のために作曲したのに対して、スヴェンセンはもっぱら大編成の、とりわけオーケストラの作曲家であった。最も有名な作品は、ヴァイオリンと管弦楽のためのロマンスである。存命中は、作曲家や指揮者として非常に人気があり、国から数々の栄誉を授けられた。
ジョゼフ・コズマ
1905年10月22日 - 1969年8月7日
ハンガリー

ジョゼフ・コズマ(Joseph Kosma; ハンガリー語:Kozma József [ˈkozmɒ ˌjoːʒɛf](コズマ・ヨージェフ), 1905年10月22日 ブダペスト - 1969年8月7日 パリまたはラ・ロシュ・ギヨン)は、ハンガリー出身の作曲家。ユダヤ人であったため、1933年にナチス・ドイツを避けてパリに定住。1936年より音楽家としてフランス映画界に進出。1946年にフランスに帰化した。
さだまさし
1952年4月10日
日本

日本のシンガーソングライター、俳優、タレント、小説家。國學院大學、東京藝術大学客員教授[5][6]。ファンとスタッフの間では「まっさん」の愛称で親しまれている。フォークデュオのグレープでメジャーデビュー。「精霊流し」のヒットにより全国にその名を知られるようになった。ソロシンガーになってからも「雨やどり」「案山子」「関白宣言」「道化師のソネット」「親父の一番長い日」「北の国から〜遥かなる大地より〜」など、数々のヒット曲を生み出す。2019年10月6日時点で、日本で最も多くのソロ・コンサートを行った歌手でもあり、その回数は4,400回を越えている。トークの軽妙さは大きな魅力とされており、それで自身のコンサートのお客を楽しませ、またテレビ・ラジオ番組のパーソナリティーやMCなどとしても活躍。小説家としても活動し、『解夏』『眉山』などの作品を発表している。
ポール・ボノー
1918年9月14日 - 1995年5月1日
フランス

セーヌ=エ=マルヌ県モレ・シュル・ロワン出身。パリ音楽院に入学し、和声をジャン・ギャロンに、フーガをノエル・ギャロンに、作曲をアンリ・ビュッセルに師事した。 1939年に陸軍に入り、1945年に軍楽隊長に就任した。しかしラジオ・フランスの軽音楽部門の指揮者の仕事に専念するため退役した。ラジオ・フランスでは1944年から30年間で638曲を指揮した。また1959年に「レ・ジーン・シンガーズ」という合唱団を創設し、指導にあたった。 作品には『サクソフォーン協奏曲』『ニューヨークのフランス人』などの管弦楽曲のほか、11のバレエ音楽、51の映画音楽などがある。
橋本國彦
1904年9月14日 - 1949年5月6日
日本

橋本 國彦(はしもと くにひこ、Qunihico Hashimoto、1904年9月14日 - 1949年5月6日)は、日本の作曲家、ヴァイオリニスト、指揮者、音楽教育者。 東京都本郷生まれ。ヴァイオリンを辻吉之助に師事。北野中学校(現:大阪府立北野高等学校)を経て、1923年(大正12年)東京音楽学校(現:東京芸術大学)入学。安藤幸とヨゼフ・ケーニヒにヴァイオリンを、チャーレス・ラウトロプに指揮法を学ぶ。作曲は信時潔に指導を受けるもほとんど独学であったが、同校研究科で作曲を学ぶ。歌曲『お菓子と娘』『黴』などで作曲家としての名声を獲得。斬新な曲を作る一方ではポピュラーなCM曲や歌謡曲にも手を染めた。
アルフレート・シュニトケ
1934年11月24日 - 1998年8月3日
ソビエト連邦

ヴォルガ・ドイツ人自治共和国のエンゲリスに生まれる。 ジャーナリストおよび翻訳家の父親は、1926年にヴァイマル共和国からソビエト連邦に移住してきたフランクフルト出身のユダヤ系ドイツ人で、母親はいわゆるヴォルガ・ドイツ人。このためシュニトケは、少年時代からドイツ語を使う家庭環境に育つ(ただし母語はヴォルガ・ドイツ方言であった)。 1946年に父親の赴任地ウィーンで最初の音楽教育を受ける。1948年にモスクワに転居。1961年にモスクワ音楽院を卒業し、翌1962年から1972年まで講師を務めた。その後は主に映画音楽の作曲により糊口をしのぐ。後にカトリックに改宗し、信仰心が作風の変化に影響を与えるが、合唱協奏曲に明らかなように、シュニトケ自身は共産革命を経ても猶ロシアに根付いているロシア正教会の力強い神秘主義に親近感を持っていた。
レオ・ブローウェル
1939年3月1日
キューバ

ハバナ出身。彼の祖母は作曲家のエルネスティーナ・レクオーナ・イ・カサド。アメリカ合衆国に留学し、ハートフォード大学、さらにジュリアード音楽学校で学ぶ。ジュリアード音楽学校ではステファン・ウォルペに師事。初期の作品はキューバの民俗音楽の影響を示している。しかし1960年代から1970年代にかけてルイージ・ノーノやヤニス・クセナキスのような現代音楽の作曲家に興味を持ち、「ソノグラマ1」のような作品では不確定要素を取り入れている。この時期の他の作品には「雅歌」(1968年)、「永遠の螺旋」(1971年)、「パラボラ」(1973年)、「狂おしい思い」(1974年)などがある。近年では調性と形式美に傾き、ギター独奏曲の「黒いデカメロン」(1981年)、「鐘のなるキューバの風景」(1987年)、「ソナタ」(1990年、ジュリアン・ブリームに献呈)などでその傾向を示している。 ギタリストとしては1980年代まで活動していたが、右手中指の腱を痛めたのがもとで以降は指揮活動を中心に活動している。
チャールズ・アイヴズ
1874年10月20日 - 1954年5月19日
アメリカ

チャールズ・エドワード・アイヴズ(Charles Edward Ives、1874年10月20日 コネチカット州ダンベリー - 1954年5月19日 ニューヨーク市)は、アメリカ合衆国の作曲家。アメリカ現代音楽のパイオニアとして認知されている。作品は存命中はほとんど無視され、長年演奏されなかった。 現在では、アメリカ的な価値観のもとに創作を行なった独創的な作曲家と評価されており、録音もかなりの数が存在する。作品にはさまざまなアメリカの民俗音楽の要素が含まれている。
PRおすすめのコンサート

第22回みなとみらいアイメイトチャリティーコンサート

石田泰尚(ヴァイオリン)と上原彩子(ピアノ)によるチャリティーコンサート