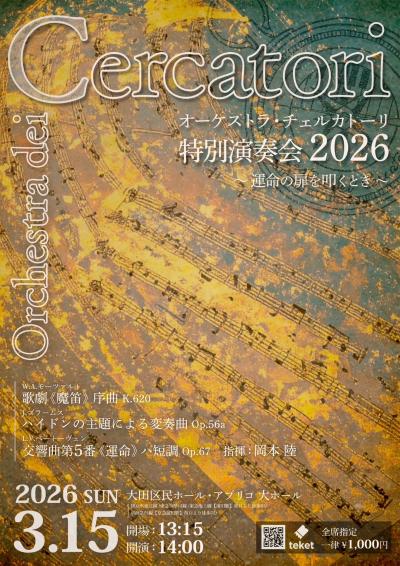作曲家検索
作曲家一覧
711-720件 / 1157件中
野本洋介
日本

1981年生まれ。千葉県出身。東京藝術大学器楽科卒業。 これまでに打楽器を菅原淳、有賀誠門、岡田知之、高田みどり、石内聡明の各氏に、音楽学を小山薫氏に師事。 「お寿司のわさび」的オケマンと「かゆいところに手が届く」的作編曲家を目指し、日々譜読みと〆切に追われている。 別府アルゲリッチ音楽祭、北九州国際音楽祭、東京・春・音楽祭等に出演。 第16回「国際音楽の日」コンサート(千葉市音楽協会主催)ではソリストとして自作の打楽器独奏と吹奏楽のためのコンチェルトを演奏。 第12回千葉市芸術文化新人賞受賞。 JPC(コマキ楽器)より打楽器アンサンブル曲を出版、全国で演奏されている。 現在、読売日本交響楽団打楽器奏者。横浜シンフォニエッタ、メンバー。 洗足学園音楽大学講師。
ルイ・ガンヌ
1862年4月5日 - 1923年7月13日
フランス

ルイ・ガンヌ(Louis Ganne, 1862年4月5日 - 1923年7月13日(7月14日説あり))は、フランスの劇場指揮者でオペラ作曲家。軍隊行進曲の作曲家としても名高い。本名はルイ=ガストン・ガンヌ(Louis-Gaston Ganne)
ヨーク・ボウエン
1884年2月22日 - 1961年11月23日
イギリス

エドウィン・ヨーク・ボウエン(Edwin York Bowen、1884年2月22日 - 1961年11月23日)は、イギリスの作曲家。 ロンドンのクラウチ・エンド出身。王立音楽アカデミーで学び、後に同校の教授となった。 後期ロマン派のスタイルで作曲し、すばらしいピアニストそして多作でマイナーな作曲家として認識された。イギリス音楽界でのボウエンの評価は若いころから第一次世界大戦までは高かったが、アーノルド・バックスのような現代的な語法の作曲家が好意的な評価を受けるとともに、彼の評価は低下していった。 管弦楽曲、ピアノ協奏曲、ピアノ曲、室内楽曲を多く残した。特に、抜粋で自作自演も残しているピアノのための『24の前奏曲』はカイホスルー・シャプルジ・ソラブジに献呈され、ソラブジ自身から絶賛された。近年では、そのピアノ作品の演奏も能くするスティーヴン・ハフの校訂によるピアノ曲の楽譜が出版されている。
ルッツァスコ・ルッツァスキ
1607年9月11日
イタリア

ルッツァスキの生年に関して詳しい事はわかっていないが、おそらくはフェラーラで生まれ、一生をフェラーラで過ごしたと考えられている。ルッツァスキ本人の証言によれば、彼は若い頃チプリアーノ・デ・ローレの弟子であったという。1561年には宮廷オルガニストとして採用され、1564年に前任者のジャッケス・ブリュネルが死去すると、首席オルガニストに就任した。以後、アルフォンソ2世が死去する1597年までこの地位にとどまり、宮廷の音楽活動において指導的な役割を果たした。アルフォンソ2世の死後もフェラーラにとどまって活動したと見られる。彼の葬儀には80人の音楽家が集まり、棺の上に金色の月桂樹のリースがのせられたという。
カール・チェルニー
1791年2月21日 - 1857年7月15日
オーストリア

オーストリアの作曲家、ピアニスト、ピアノ教師。ベートーヴェン、クレメンティ、フンメルの弟子で、リストおよびレシェティツキの師。作風は初期ロマン派の傾向に留まった。デビュー後のリストの演奏様式に懐疑的であった時期もあるが、ショパンやリストのような後代の作曲家の斬新性を高く評価し、彼らの編曲や校訂活動を熱心に行った。作品番号は861に上り、未出版のものを含めて1,000曲以上の作品を残した多作家であったが、現在は実用的なピアノ練習曲を数多く残したことで有名な存在である。
横山幸雄
1971年2月19日
日本

横山 幸雄(よこやま ゆきお、1971年2月19日 - )は、日本のクラシック音楽のピアニスト、作曲家。 ピアノを伊達純、アンリエット・ピュイグ=ロジェに[1]、作曲とソルフェージュを永冨正之に学ぶ[2]。1987年に東京芸術大学音楽学部附属音楽高等学校在学中にパリ国立高等音楽院にフランス政府給費留学生として留学。ジャック・ルヴィエ、ヴラド・ペルルミュテール、パスカル・ドヴァイヨンに師事。1990年にパリ国立高等音楽院卒業。2003年から2017年3月13日まで上野学園大学教授。
浜渦正志
1971年9月20日
日本

浜渦 正志(はまうず まさし、1971年9月20日 - )は、日本の作曲家、編曲家、音楽プロデューサー、映像作家、デザイナー、フォトグラファー、DTPデザイナー、脚本家。ドイツ・ミュンヘン出身。IMERUATのメンバー。元スクウェア・エニックス所属。 1971年、両親の留学中にドイツ・ミュンヘンにて出生。父は声楽家の浜渦章盛で自ら合唱団を主催し、正志も幼少より同団に所属していた。1991年、東京藝術大学音楽学部声楽科に進学。1996年にスクウェア(現・スクウェア・エニックス)に入社、ファイナルファンタジーシリーズ、サガシリーズを始め数々のゲーム音楽を担当。2009年全編担当した『ファイナルファンタジーXIII』の音楽では世界的な評価を受け、サウンドトラックもオリコン初登場3位を記録。ヨーロッパ、北米各国でのオーケストラコンサートシリーズにも作曲・編曲で参加している。
カール・フリードリヒ・アーベル
1723年12月22日 - 1787年6月20日
ドイツ

カール・フリードリヒ・アーベル(Carl Friedrich Abel, 1723年12月22日 - 1787年6月20日)は、ドイツ出身の作曲家。ヴィオラ・ダ・ガンバの名手であり、貴重な作品を残した。アンハルト=ケーテン公国(ドイツ語版)のケーテンに生まれる。父親のクリスティアン・フェルディナンド・アーベルは、ヨハン・ゼバスティアン・バッハが楽長を務めていた時のケーテン宮廷楽団の首席ヴィオラ・ダ・ガンバおよびチェロ奏者だった。ライプツィヒのギムナジウム Thomasschule で学んだと言われる。
ジョン・スティーブンス
アメリカ

ジョン・D・スティーブンス(1951年生まれ)は、アメリカの作曲家/アレンジャー、チューバ奏者、真鍮の 教育学者です。彼はウィスコンシン大学マディソン校にある金管五重奏団である金管五重奏団と共演しています。
ヴィルヘルム・ステーンハンマル
1871年2月7日 - 1927年11月20日
スウェーデン

カール・ヴィルヘルム・エウフェーン・ステーンハンマル(ステンハンマルとも、Carl Wilhelm Eugen Stenhammar, 1871年2月7日 - 1927年11月20日)は スウェーデンの作曲家、ピアニスト、指揮者。
PRおすすめのコンサート

第22回みなとみらいアイメイトチャリティーコンサート

石田泰尚(ヴァイオリン)と上原彩子(ピアノ)によるチャリティーコンサート